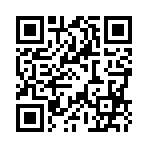八十難の臨床解説、
2014年06月22日

難経 第八十難
ゆっくり堂の『難経ポイント』 第八十難 ank080
※ 八十難のポイント其の一、
難経、八十難は「気を感知」して、刺入と抜鍼を行う刺鍼法の法則が展開されています。
※ 八十難のポイント其の二、
刺入の法則とは、気が現われた事を感じて、その後に刺入すること。
※ 八十難のポイント其の三、
抜鍼の法則とは、補法でも瀉法でも気の変化が現われた事を感じて、その後に抜鍼すること。
※ 八十難のポイント其の四、
難経、八十難を本当に理解するには「気を集める」鍼の技術がないと知る事が出来ません。
※ 八十難のポイント其の五、
左手(押手)に「気が来る」事が本当に判るには、
右手(刺手)で鍼をを微細に動かす弾法や撚法などの「気を集める」技術が必要です。
※ 八十難の臨床解説、
「五十肩痛の改善例」ゆっくり堂鍼灸院の臨床例から、難経八十難を解説します。
※ 井上恵理先生の難経、第八十難の解説:経絡鍼療(501号)よりの抜粋を掲載しています。
(井上恵理先生の難経、第八十難の解説を参考にして山口一誠が文章を構成しています。)
--------------------------
難経 第八十難 原文
八十難曰.
經言.
有見如入.有見如出者.何謂也.
然.
所謂有見如入者.
謂左手見氣來至.乃内鍼.
鍼入見氣盡.乃出鍼.
是謂有見如入.有見如出也.
(『難経』原本は底本:『難経』江戸・多紀元胤著、『黄帝八十一難経疏証』(国立国会図書館所蔵139函65号)オリエント出版、難経古注集成5(1982年)に影印)を参考にしています。
--------------------------
八十難の訓読
(井上恵理先生の解説:経絡鍼療(501号)と本間祥白先生の解説、福島弘道先生の解説を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
八十難に曰く。
経に言う。
見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て入れ、
見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て出(いだ)すとは、
何(なん)の謂(いい)ぞや。
然(しか)るなり。
所謂(いわゆ)る見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て入れるとは、
謂(いわゆ)る左手に見(あらわ)るる氣来り至(いた)って、乃ち鍼を内(い)れ、
鍼入れて見(あらわ)るる気尽きて、乃ち鍼を出(いだ)す。
是(こ)れ見るること有て如て入れ、見るること有て如て出すと謂(い)うなり。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
--------------------------
八十難の解説
(井上恵理先生の解説:経絡鍼療(501号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
八十難の解説をします。
難経理論から考察すると。
気が現われて、気を感じた後に、鍼を刺入するとあり、
刺入した鍼尖に新たに気の変化が現われ、あるいは気の充実を感じたら抜鍼するとは、
如何なる手法であるか、またその生体現象を説明しなさい。
お答えします。
気が現われる事が有って、後に鍼を刺入すると言うことは、
鍼尖を穴に接触して気を得る手技をしていると、
押手(左手)に気が来るのを感じる事ができ、そこに至った後に鍼を刺入しなさいと。
鍼の刺入中に気の変化が現われた後に、抜鍼しなさいと。
瀉法の場合の、「気尽きて」の意味は、『充実した気が無くなった時』に鍼をソーッと抜く事。
補法の場合の、「気尽きて」の意味は、『気が充実し尽した時』に鍼をすばやく抜く事。
気が現われた後に刺入し、補法・瀉法の変化が現われた後に抜鍼する。
これが八十難の法則ですと。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
--------------------------
八十難の詳細解説
(井上恵理先生の訓読・解説:経絡鍼療(501号)と本間祥白先生の訓読・解釈、福島弘道先生の訓読・解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)詳しくは各先生の文献を参照されたし。
山口一誠の考察により原文・訓読・解説(解説補足)の順に文章を構成します。
〔原文〕八十難曰.
〔訓読〕八十難に曰く。
〔解説〕八十難の解説をします。
〔原文〕經言.
〔訓読〕経に言う。
〔解説〕難経理論から考察すると。
〔原文〕有見如入.有見如出者.何謂也.
〔訓読〕見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て入れ、
見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て出(いだ)すとは、
何(なん)の謂(いい)ぞや。
〔解説〕気が現われて、気を感じた後に、鍼を刺入するとあり、
刺入した鍼尖に新たに気の変化が現われ、あるいは気の充実を感じたら抜鍼するとは、
如何なる手法であるか、またその生体現象を説明しなさい。
〔解説補足〕ここは、補瀉の手技において、押手、刺手での操作により、気の変化を感じての、
刺入・抜鍼の頃合いがありますが、その説明を求めています。
〔原文〕然.
〔訓読〕然(しか)るなり。
〔解説〕お答えします。
〔原文〕所謂有見如入者.
謂左手見氣來至.乃内鍼.
鍼入見氣盡.乃出鍼.
是謂有見如入.有見如出也.
〔訓読〕所謂(いわゆ)る見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て入れるとは、
謂(いわゆ)る左手に見(あらわ)るる氣来り至(いた)って、乃ち鍼を内(い)れ、
鍼入れて見(あらわ)るる気尽きて、乃ち鍼を出(いだ)す。
是(こ)れ見るること有て如て入れ、見るること有て如て出すと謂(い)うなり。
〔解説〕
気が現われる事が有って、後に鍼を刺入すると言うことは、
鍼尖を穴に接触して気を得る手技をしていると、
押手(左手)に気が来るのを感じる事ができ、そこに至った後に鍼を刺入しなさいと。
鍼の刺入中に気の変化が現われた後に、抜鍼しなさいと。
瀉法の場合の、「気尽きて」の意味は、『充実した気が無くなった時』に鍼をソーッと抜く事。
補法の場合の、「気尽きて」の意味は、『気が充実し尽した時』に鍼をすばやく抜く事。
気が現われた後に刺入し、補法・瀉法の変化が現われた後に抜鍼する。
これが八十難の法則ですと。
--------------------------
〔解説補足〕
ゆっくり堂鍼灸院の臨床例から、難経八十難を解説します。
女性51歳、主訴は右の五十肩様の痛み。夜間痛あり。(1年前より。)
可動域角度:肩関節前方挙上角度100度。 肩甲帯屈曲10度でロックされ伸展できない。
(寝床に肩が着かない、肩が前に出ている状態。)この可動域を超えると痛みが出る。
切経:右肩背部の肩リョウ穴から天リョウ穴のライン上の、2か所に母指大の硬結圧痛部位がある。
当院は経絡鍼灸の手技を基本としていますので本治法と標治法の処置で病状改善を行っていますが、
今回の記述は、標治法の手技のみを述べて、難経八十難の臨床的解説してみます。
硬結圧痛部位に対する標治法から、
施術に使用した鍼は、銀鍼の9×8-2番です。
① 右肩背部の、母指大の硬結圧痛部位に対して、浅補深瀉の手法で施術を処置しました。
1、刺鍼の手法。(撚鍼法にて。)
2、押手(左手)を構え、鍼尖を痛みなくゆっくりと穴に接触。
3、刺手(右手)の手法は、示指を下にして母指を上に位置して、鍼柄を柔らかく挟み。
4、挟んだ鍼柄を示指は動かさず、母指のみを鍼尖の方向にむけて、鍼柄を撫でる手法を施す。
※ この「鍼柄を撫でる」手技は鍼尖の部位に催気を促す事なのだと思います。
「鍼柄を撫でる」手技を3秒~10秒ほど、撫でる回数では10回~30回ほど、やっていますと、
催気(氣來至)を感じます。
(鍼尖に気が集まる感じ、気が来る感じ、を知覚します。)
(気の形状は金平糖様で、直径1ミリぐらいです。そこに僅かに温かみも出て来ます。)
5、気を得た様に感じたら、鍼柄を軽く挟み、ソーッと押すと鍼尖が刺入し進んで行きます。
※ これら一連の認知行動が、難経八十難の「刺入の法則」ことだと思います。
〔原文〕『謂左手見氣來至.乃内鍼.』
〔訓読〕謂(いわゆ)る左手(押手)に見るる氣来り至(いた)って、乃ち鍼を内(い)れる。
〔解説〕押手(左手)に気が来るのを感じる事ができ、そこに至った後に鍼を刺入しなさいと。
6、浅補部にて、充分に補法を行い。さらに鍼尖が進むと目的の硬結部位に到達する。
7、硬結部位に到達したらこの硬結を緩める手技として、鍼の抜き差し旋回を施します。
8、硬結部位の緩めが完了したら、(邪実した気が無くなった時)
9、深瀉部はゆっくりとソーッと鍼を引き上げ、
10、浅補部からは押手の左右圧をスーッ加え、すばやく抜鍼と同時に、鍼口を閉じる補法を行う。
※ そしてこれがまた、難経八十難「抜鍼法則」の臨床になると思います。
〔原文〕「鍼入見氣盡.乃出鍼.」
〔訓読〕鍼入れて見(あらわ)るる気尽きて、乃ち鍼を出(いだ)す。
〔解説〕鍼の刺入中に気の変化が現われた後に、抜鍼しなさいと。
瀉法の場合の、「気尽きて」の意味は、『充実した気が無くなった時』に鍼をソーッと抜く事。
補法の場合の、「気尽きて」の意味は、『気が充実し尽した時』に鍼をすばやく抜く事。
追記:この患者さんの場合は、週に1回の治療をしています。
来院7回目の肩関節可動域角度を点検しましたところ、
患者の病状は、次のように改善されています。
可動域角度:肩関節前方挙上角度170度・肩肩甲帯伸展屈曲各20度で正常になる。
肩の痛み、夜間痛は消失しています。
--------------------------
〔井上恵理先生の難経、第八十難の解説:経絡鍼療(501号)より、抜粋。〕
※ 難経、八十難は「鍼を刺す時の鍼師の心構え・考え方」を顕している。
「見(あらわ)るること有(あっ)て如(しかし)て入れ、」とは、
この刺入の法則には鍼師の術の手技の前段行為がある。
ツボを探ったならば、そこをよく撫で擦って押して或は叩いて弾いて、
そこに気を「集める事」を第一の段階とする。
そして第二の段階として、気が現われて、気を感じた後に、鍼を刺入するのだと。
「気尽きて乃ち鍼を出す」とは、
例えば、
瀉法の場合の、「気尽きて」と言う事は、『充実した気が無くなった時』に鍼を出す。
補法の場合の、「気尽きて」と言う事は、『気が充実し尽した時に』鍼をソーッと抜く。
「気」は全て左手(押手)に感ずる事なのだと。
左手(押手)に感ずる所の気の虚実・気の出入りあるいは気の充実と言う事を無視して、
ただ鍼を入れさえすればいいのだと言うのは間違いなんです。
本治法の五井穴の治療に於いて最も良く判る事ですね。
五井穴には殆ど脉があります。ですから虚している時に補う方法を取ると、
初め鍼を刺す時 には幾ら撫で擦ってもなかなか脉は出て来ない。
ところが鍼を刺して弾法をし或は捻法をし、或は静かに動かす事によって脉がポコッと、
出てくる事がある。ここに取ればいい。
或は柔らかく感じた所が左手の親指の下に重く感じた時に鍼を抜く。
何故左手で押さえながら右手で鍼を弾いたり撚法したり右手を動かすのかと。
※ これは我々の意識を右の手に用いるから、
右の手を動かさないと左手に「気が」来る事が判らない。
※ 右の手を動かす事によって左手の方が何かを診ると言う力が無くなる。
虚無の状態になる。
そこで初めて本当の鍼の気の来る事が判る。
※ 左手(押手)に「気が」来る事が本当に判るには、
右手で鍼を弾いたり撚法したり右手を動かす事であると。
--------------------------
そのほかの、
難経解説をご覧になりたい方は、
こちらのHPをご覧ください。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
----------------------------------------
掲載日:2014.6.22.
微妙微細な鍼術 七十九難
2014年06月18日

難経 第七十九難
ゆっくり堂の『難経ポイント』 第七十九難 ank079
※ 七九難のポイント其の一は、
「得るが若く、失が若し」の感性が鍼灸師の腕を左右します。
補瀉の処置で微妙な虚実の「得るが若く、失が若し」の感覚があります。
それは、
補法を行った時には、何かが出てきたような感じ。なかったものが有る様な感じ。
補法はあくまでも生気を補われ、身体が少し満たされる様な感じを覚える状態かな。
瀉法を行った時には、有った物が無くなった様な感じを覚える。
瀉法は身体に必要ないものが無くなり、身体が楽になった様な感じを覚える状態かな。
難経 第七九難 原文
七十九難曰.
經言.
迎而奪之.安得無虚.
隨而濟之.安得無實.
虚之與實.若得若失.
實之與虚.若有若無.何謂也.
然.
迎而奪之者.瀉其子也.
隨而濟之者.補其母也.
假令心病.瀉手心主兪.是謂迎而奪之者也.
補手心主井.是謂隨而濟之者也.
所謂實之與虚者.牢濡之意也.
氣來實牢者爲得.濡虚者爲失.故曰若得若失也.
(『難経』原本は底本:『難経』江戸・多紀元胤著、『黄帝八十一難経疏証』(国立国会図書館所蔵139函65号)オリエント出版、難経古注集成5(1982年)に影印)を参考にしています。
--------------------------
七九難の訓読
(井上恵理先生の解説:経絡鍼療(498号)と本間祥白先生の解説、福島弘道先生の解説を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
七十九難に曰く。
経に言う。
迎(むか)えて之を奪わば、 安(いずくんぞ)虚なきことを得ん、
隨(したが)って之を濟(すく)わば、 安(いずくんぞ)実なきことを得ん。
虚と実とは、得(う)るが若(ごと)く、失(うしな)が若(ごと)し。
実と虚とは、有が若く無が若しとは、何の謂(いい)ぞや。
然(しか)るなり。
迎えて之を奪うとは、其の子を瀉するなり。
隨って之を濟うとは、其の母を補うなり。
假令(例え)ば心病は、手の心主の兪を瀉す、是れ謂(いわゆ)る迎えて之を奪うものなり。
手の心主の井を補う、是れ謂る隨って之を濟うものなり。
いわゆる実と虚とは、牢(ろう)濡(なん)の意なり。
氣來ること、実牢なるものを得るとなし、濡虚なるものを失となす。
故に曰く、得るが若く、失が若しと。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
------------------
七九難の解説
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(498号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
七十九難の解説をします。
黄帝内経・霊枢・九鍼十二原篇から考察するに。
迎えて之(邪実)を奪わば(瀉法すれば)、実が取れて身体は平常の健康体に成ります。
隨って之(虚)を濟わば(補法すれば)、生気が補われ身体は平常の健康体に成ります。
補瀉の処置で微妙な虚実の「得るが若く、失が若し」の感覚があります。
それは、
補法を行った時には、何かが出てきたような感じ。なかったものが有る様な感じ。
補法はあくまでも生気を補われ身体が少し満たされる様な感じを覚える状態かな。
瀉法を行った時には、有った物が無くなった様な感じを覚える。
瀉法は身体に必要ないものが無くなり身体が楽になった様な感じを覚える状態かな。
病証としての虚と実は有るようで無いような物とう言うが、これについて説明しなさい。
お答えします。
五行の相生循環に於いての迎隨。
心病を例にとって自穴内の相生循環に於いて、木火土の関係にての迎瀉・隨補です。
迎瀉の手法:心病の栄火自穴に対して兪土原子穴(大陵穴)の施術は「其の子を瀉す」
「前の方のツボ」「経の流れの前から瀉す」「迎えて之(邪実)を奪う」と言う事になります。
隨補の手法:心病の栄火自穴に対して井木母穴(中衝穴)の施術は「其の母を補う」
「後ろから助ける」「経に随って補法」「隨って之(生気)を濟(すく)う」事になります。
所謂る実と虚とは、硬い所、軟らかい所の意味です。
軟らかい所を、崔気し、生気を充実すれば、「得るが若き」補法となる。
硬結を緩める手技は「失ったが若し」の瀉法となる。
この様に、古より鍼術は微妙微細な「得るが若く、失が若し」の感性が必要ですと。
西暦2014年の現在では難経の時代よりも更に微妙微細な「故曰若得若失也」の鍼術が必要ですね。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
--------------------------
七九難の詳細解説
(井上恵理先生の訓読・解釈:経絡鍼療(498号)と本間祥白先生の訓読・解釈、福島弘道先生の訓読・解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)詳しくは各先生の文献を参照されたし。
山口一誠の考察により原文・訓読・解説(解説補足)の順に文章を構成します。
〔原文〕七十九難曰.
〔訓読〕七十九難に曰く。
〔解説〕七十九難の解説をします。
〔原文〕經言.
〔訓読〕経に言う。
〔解説〕黄帝内経・霊枢・九鍼十二原篇から考察するに。
〔原文〕迎而奪之.安得無虚.
隨而濟之.安得無實.
〔訓読〕迎(むか)えて之を奪わば、 安(いずくんぞ)虚なきことを得ん、
隨(したが)って之を濟(すく)わば、 安(いずくんぞ)実なきことを得ん。
〔解説〕迎えて之(邪実)を奪わば(瀉法すれば)、実が取れて身体は平常の健康体に成ります。
隨って之(虚)を濟わば(補法すれば)、生気が補われ身体は平常の健康体に成ります。
〔解説補足〕補瀉には迎隨(げいずい)と言う手法がある。
〔原文〕虚之與實.若得若失.
〔訓読〕虚と実とは、 得(う)るが若(ごと)く、失(うしな)が若(ごと)し。
〔解説〕補瀉の処置で微妙な虚実の「得るが若く、失が若し」の感覚があります。
それは、
補法を行った時には、何かが出てきたような感じ。なかったものが有る様な感じ。
補法はあくまでも生気を補われ身体が少し満たされる様な感じを覚える状態かな。
瀉法を行った時には、有った物が無くなった様な感じを覚える。
瀉法は身体に必要ないものが無くなり身体が楽になった様な感じを覚える状態かな。
〔原文〕實之與虚.若有若無.何謂也.
〔訓読〕実と虚とは、有が若く無が若しとは、何の謂(いい)ぞや。
〔解説〕病証としての虚と実は有るようで無いような物とう言うが、これについて説明しなさい。
〔解説補足〕ここでの虚実は「病証」です。
〔原文〕然.
〔訓読〕然(しか)るなり。
〔解説〕お答えします。
〔原文〕迎而奪之者.瀉其子也.
隨而濟之者.補其母也.
假令心病.瀉手心主兪.是謂迎而奪之者也.
補手心主井.是謂隨而濟之者也.
〔訓読〕迎えて之を奪うとは、其の子を瀉するなり。
隨って之を濟うとは、其の母を補うなり。
假令(例え)ば心病は、手の心主の兪を瀉す、是れ謂(いわゆ)る迎えて之を奪うものなり。
手の心主の井を補う、是れ謂る隨って之を濟うものなり。
〔解説〕五行の相生循環に於いての迎隨。
心病を例にとって自穴内の相生循環に於いて、木火土の関係にての迎瀉・隨補です。
迎瀉の手法:心病の栄火自穴に対して兪土原子穴(大陵穴)の施術は「其の子を瀉す」
「前の方のツボ」「経の流れの前から瀉す」「迎えて之(邪実)を奪う」と言う事になります。
隨補の手法:心病の栄火自穴に対して井木母穴(中衝穴)の施術は「其の母を補う」
「後ろから助ける」「経に随って補法」「隨って之(生気)を濟(すく)う」事になります。
〔解説補足〕 1、 迎隨(げいずい)と言う言葉には2つの捉え方がある。
1-1:経絡の流注に対しての刺鍼の方向での迎隨。
①経絡の流れる方向に迎う刺鍼は瀉法です。 (迎瀉)(経に逆らって瀉法)
②経絡の流れる方向に隨っての刺鍼は補法です。(隨補)(経に随って補法)
1-2:五行の相生循環に於いての迎隨。
心病を例にとって自穴内の相生循環に於いて、木火土の関係にての(迎瀉隨補)です。
①迎瀉の手法:心病の栄火自穴に対して兪土原子穴(大陵穴)の施術は「其の子を瀉す」
「前の方のツボ」「経の流れの前から瀉す」「迎えて之(邪実)を奪う」と言う事になります。
②隨補の手法:心病の栄火自穴に対して井木母穴(中衝穴)の施術は「其の母を補う」
「後ろから助ける」「経に随って補法」「隨って之(生気)を濟(すく)う」事になります。
〔原文〕所謂實之與虚者.牢濡之意也.
氣來實牢者爲得.濡虚者爲失.
故曰若得若失也.
〔訓読〕いわゆる実と虚とは、牢(ろう)濡(なん)の意なり。
氣來ること、実牢なるものを得るとなし、濡虚なるものを失となす。
故に曰く、得るが若く、失が若しと。
〔解説〕所謂る実と虚とは、硬い所、軟らかい所の意味です。
軟らかい所を、崔気し、生気を充実すれば、「得るが若き」補法となる。
硬結を緩める手技は「失ったが若し」の瀉法となる。
この様に、古より鍼術は微妙微細な「得るが若く、失が若し」の感性が必要ですと。
〔解説補足〕ここでは、病症の診断的にも治療法的にも「牢濡」の説明です。
①診断的「牢濡」とは、身体を切経(触診診断)して、
堅牢なる(硬い)所、ここを実と言い、濡なる(軟らかい)所、ここを虚と言う。
脉診に於いても、同様に牢濡、虚実があります。
②治療法的「牢濡」と「得るが若く、失が若し」とは、
②-1:堅牢なる(硬い)所に、瀉法を行い軟らかくすれば、即ち「失ったが若し」となる。
本治法において、堅い脉を幾分でも柔らかくできれば「失ったが若し」の瀉法となる。
標治法においても、硬結を緩める手技は「失ったが若し」の瀉法となる。
②-2:濡なる(軟らかい)所を、崔気し、生気を充実すれば、「得るが若き」補法となる。
西暦2014年の現在では難経の時代よりも更に微妙微細な「故曰若得若失也」の鍼術が必要ですね
詳しくはこちらのHPの下段の
初学者用経絡鍼灸教科書の
難経コーナーからご覧ください。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
胸の痛み
2014年06月14日
ゆっくり堂鍼灸院の治療例です。 心旺実証例 e3041
※ 短編小説「治療日記」風に書いています。
----------------------------------

題名1、「胸の痛み」
M様が、黒塗りのベンツSクラスの新車で3ケ月ぶりのご来院です。
病状は極度の胸痛症でした。
患者M様に診療ベットに仰向けに寝てもらい。
院長の山ちゃん先生は、
「一番痛い所を触ってみてください」とお願いしました。
みぞおちの所に本人の右人差し指が軽く触れた時、
ギャーッと悲鳴を上げ痛みを強く訴えられました。
山ちゃん先生は考えます。
『これは心のバランスが崩れた為の痛みである』と。
M様は体調管理の為に当院に3年来、定期的な来院をされています。
退職した会社に依頼されて、「社歴100年の社史編纂」中とのこと、
元来几帳面な方で、あいまいさを嫌われます。
痛みには2種類の分類があります。
①外因性の痛み。
打撲などの外からの外力や農作業など力仕事で出る痛み、
これを「実邪痛」と言います。
②内因性(精神的)な痛み。
内因(精神)のバランスが崩れた為に出る痛み、
これを「旺気実痛」と言います。
M様の場合は、腎経と心経のバランスが崩れた為に痛みが出ています。
社史編纂室総合顧問を引き受けての連日業務と、
部下の取集録も全て点検する。
また、パソコン入力業務も自分でしている。
3ケ月前ほどから、疲れ易い。足が冷える。
眠りが浅く多夢あり、寝不足。夜間尿2~3回あり、
などの腎経をすり減らす「虚」の心労と症状がありました。
これは、腎経が「虚」の症状になって、
心経の「胸の痛み」になつたと診断できます。
よって、内因(心)のバランス整える鍼灸治療を施す事になります。
診断名は「心旺実証」です。
この様な場合に使用する鍼は「テイ鍼」と言うもの使用します。
「テイ鍼」は爪楊枝の2倍ぐらいの長さの物で、金で出来ています。
皮膚のツボに当てるだけで、皮膚の中に鍼が刺さる事はありません。
「難経」第七十五難の現代的な解釈理論から、
治療ほ施すツボは、
本治法として、左足の厥陰肝経の「曲泉穴」です。
手技は「曲泉穴」に左手の人差し指と親指をそっと当て、
右手の人差し指と親指に「テイ鍼」尾部をそっと挟み、
垂直に曲泉穴の左手の人差し指と親指の間にそっと頭部を下ろしていきます。
しばらくすると曲泉穴と「テイ鍼」の頭部に「心地よい温かみのある感じを覚えます。」
これは曲泉穴が補法され、気が充実してきたものです。
患者さんの苦悶の顔も和らいで、呼吸も楽になったころあいに、
「テイ鍼」をそっと引き抜き1本目の治療は終了です。
そして、脉を診ますと、堅く引きつり荒々しく凸凹にうねっていた脉状が、
緩(おだ)やかな艶とのびのある脉状に変化していました。
1本目の治療後、患者のM様に様子をお聞きしましたら、
みぞおちの痛みは半分は無くなった。
胸部全体の締め付けられるように痛も改善して、
呼吸が楽になったとの感想を頂きました。
本治法は、「曲泉穴」1本で終了します。
次に、標治法は軽く行なう事にします。
症状が激しい場合は沢山のツボを治療すると、
患者さんの身体にかえって負担をかけますから。
標治法の手技は、
患者さんを側臥位(横向きに寝てもらい)
初めに、
任脈(おへその下辺りから下唇の辺りのライン)の
曲骨穴から、承漿穴まで、
「金のテイ鍼」を皮膚と平行におき、
かつ、皮膚から1センチ離して、任脈ライン上をゆっくりと進めます。
経絡鍼灸の理論では、任脈という経絡の流れは気を司っています。
そして最後に、
督脈(尾骨下端辺りから頭の頂上を超えて鼻根を過ぎ上唇の辺りのライン)の
長強穴から齦交穴までを、
先ほどと同く「金のテイ鍼」で施術を行いました。
今回はこれで治療は終了です。
M様のお顔がいつもの理性的な笑顔に戻りました。
参考:本治法と標治法について。
本治法とは、
病気の根本原因を改善する為の施術手技です。
本治法の方法は、十二経絡の「気」を調整し、「血」の流れを順行させ、
全身の健康状態を改善することで、病気を治す「自然治癒力」を増強させる手技です。
標治法とは、
患者の病状を直接に緩和させる手技です。
標治法の方法は、体表より観察できる「虚実」の状態に対して、
「補法、瀉法」を行なって、これを調和させ病状を緩和させます。
参考HP
http://you-sinkyu.ddo.jp/e101.html
----------------------------------
これよりは、 鍼灸師及び医療専門家の皆様に公開するコーナーです。
短編治療日記風の(題名○、「内容」)同一のものを経絡鍼灸の弁証法で掲載しています。
専門家の皆様のご意見を頂ければ幸いです。
なお、このコーナーは、
「難経」第七十五難型・診断と治療の改善例(症例発表)になります。
----------------------------------
(鍼灸師及び医療専門家用) 心旺実証・その1.
題名1、「胸の痛み」
男性83歳 3年来の定期的な来院患者、初めの2年間は毎週1回の来院(主訴は右腎兪辺りの痛み)
証は腎虚証・腎脾相剋経調整証、腎と脾、時に肺に絡む証を立ての治療が多い。
ここ1年は月に1回、健康維持の為に鍼灸治療を受けていた。
今回は3ヵ月ほど間が空いての来院である。
職業:会社相談役(社史編纂室総合顧問)
初診日:x年○月21日
主訴:左右の胸部が締め付けられるように痛む。
副訴:右肩の痛み、右肘から手、指先まで、痺れと痛みあり。
上半身が熱ぽく 頭部、顔面が暑く不快。
腰から下は冷たく特に両足先が冷えを感じる。
現病歴:社歴100年につき社史編纂中、
代表取締役社長としての経験から社史編纂室総合顧問を引き受け連日業務、
部下の取集録も全て点検する。
また、パソコン入力業務も自分でしている。
3ケ月前ほどから、疲れ易い。足が冷える。眠りが浅く多夢あり、寝不足。夜間尿2~3回あり。
既往歴:腎臓結石・慢性の鼻炎・胃癌(胃の2/3切除)。
望診:顔面が赤黒く上気して眉間に皺が寄り苦悶の表情。
前かがみに歩き、動作は緩慢で胸に手を当てる。
尺部診(前腕部前面):赤茶色・艶なくざらついた感じ。
体格:身長160cm・体重56kg
舌診:舌先が赤く、痺れ苦い感覚がある。
聞診:声は短く、高く、清い。五音は徴。 話し方=五声は言。 発声法は歯お音サ行。声に艶と力がない。
臭い=五香は焦。と判定する。
問診:食欲ある。便通普通。主訴、副訴、現病歴、既往歴のこと。
特徴として既往歴の腎臓の病歴、母親も腎透析を受けていた事を繰り返し心配して話す。
切診
切経予備問診:仰臥位にて、主訴部の痛みを確認する意味で本人に一番痛く感じる部位を触るように指示した。
任脈の鳩尾穴辺りに本人の右示指が軽く触れた時、悲鳴を上げ痛みを強く訴える。
腹診:中カン穴の少し上より、鳩尾に至る心の診所、冷感・緊張しわずかに触れるだけで痛み、最も実。
陰交穴より中カン穴のやや上までの脾の診所、ザラつき軟弱で虚。
脉診
1、脉状診:浮・数・実の六祖脉を判定。
( 堅く引きつり荒々しく凸凹にうねった脉状。)
2、比較脉診:左手寸口沈めて心最も実、浮かせて小腸虚。
右手関上沈めて脾実、浮かせて胃虚。
左手尺中沈めて腎虚、浮かせて膀胱実。
左手関上沈めて肝虚、浮かせて胆実
肺は平位と診ました。
病症の経絡的弁別
心火経の変動:鳩尾穴辺りの激痛所見。主訴の胸痛。 副訴の上半身が熱ぽく 頭部、顔面が暑く不快。
脾土経の変動:疲れ易い。連日業務の働き過ぎ。
腎水経の変動:腰から下は冷たく特に両足先が冷えを感じる。眠りが浅く多夢あり、寝不足。夜間尿あり。
証決定:心旺実証に弁別する。
適応側:左を適応側とする。
(腎実の病状、腎虚の逆気に対して、気を下げる効果がある。)
予後の判定:仕事の心労から腎が虚し、心が旺実した陰旺実証であるので、
難経七十五難型の治療法が適当であり、
一過性の急性病と判断したので予後は「良」と診る。
治療方針:本治法として、
心旺実証の一番目に行われる手技を「肝経」の補法と定め、
治療効果を診ながら、
再び診察して、病状・脉状より、虚実をわきまえて、
補瀉の処置をする。
治療経過
初診:x年○月21日
本治法として、
治療穴:左足の厥陰肝経の「曲泉穴」。
「難経」第七十五難、陰旺実証の診断原則から、
其の一、陰旺実証の一番の原因は「腎経の虚」です。
其の二、そしてこの「腎経が虚した」と言う前提の上に立って、
相剋する経絡が実したと言う現象、「心旺実証」が顕れています。
よって、「難経」第七十五難、陰旺実証の治療原則から、
其の一、「旺実すればその母を補う。」
心旺実証の一番目に行われる手技は足厥陰肝経「曲泉穴」の補法です。
手技は「曲泉穴」に押手を構え、刺手に「テイ鍼」尾部をそっと挟み、
垂直に頭部を下ろしていきます。
しばらくすると曲泉穴と「テイ鍼」の頭部に「心地よい温かみのある感じを覚えます。」
これは曲泉穴が補法され、気が充実してきたものです。
患者さんの苦悶の顔も和らいで、呼吸も楽になったころあいに、
「テイ鍼」をそっと引き抜き1本目の治療は終了です。
そして、脉を診ますと、堅く引きつり荒々しく凸凹にうねっていた脉状が、
緩(おだ)やかな艶とのびのある脉状に変化していました。
1本目の治療後、患者のM様に様子をお聞きしましたら、
みぞおちの痛みは半分は無くなった。
胸部全体の締め付けられるように痛も改善して、
呼吸が楽になったとの感想を頂きました。
本治法は、「曲泉穴」1本で終了します。
「難経」第七十五難、陰旺実証の治療原則
其の二、「其の余を問わん。」
今回は本治法の「曲泉穴」補法で、
患者の病状、脉状とも改善の方向に向きましたので、
ここで本治法は終了する事になります。
標治法:
次に、標治法は軽く行なう事にします。
症状が激しい場合は沢山のツボを治療すると、
患者さんの身体にかえって負担をかけますから。
標治法の手技は、
患者さんを側臥位(横向きに寝てもらい)
初めに、
任脈の曲骨穴から、承漿穴まで、
「金のテイ鍼」を皮膚から1センチ離して、任脈ライン上をゆっくりと進めます。
この時、任脈の気を感じながらテイ鍼を進める事がポイントです。
そして最後に、
督脈の長強穴から齦交穴までを、
先ほどと同く「金のテイ鍼」で施術を行いました。
今回はこれで治療は終了です。
治療後の患者の状態:
主訴:左右の胸部痛と鳩尾穴辺の激痛は半分ほど改善する。
副訴:右肩の痛み、右肘から指先までの痺れと痛みは消失。
上半身、頭部、顔面の熱も引いている。
腰から下のも温かみが戻った。
2回目:○月24日
前回治療の患者の変化:前回の胸痛等は全て改善した。仕事も順調に進んでいるとの事。
今回は、体調維持目的で、腎虚証で治療。
考察:
陰旺実証の治療が難経六十九難型で、対応できない時、
気楽に「難経」第七十五難、陰旺実証の診断治療を行うことで、
患者の病苦を改善できた症例だと思います。
各位鍼灸家の追試をお願いできれば幸いです。
ゆっくり堂鍼灸院、鍼灸師:山口一誠。
HP掲載日:2014年6月13日(金曜日)
----------------------------------
参考資料:
心旺実証の診断と治療(陰旺実証・理論と臨床)
http://you-sinkyu.ddo.jp/e301.html
⑤ 一番の原因:腎虚
〔腎虚の症状〕: 心が脅かされ、恐れ慄いて心休まず、身痩せて心身ともに衰弱する。
足腰が立たない、動けない、わずかの光、小さな音などに恐れおののく。
腎経の虚は人を老いさせ、日常生活が過ごし難く、慢性疲労症候群に似た状態になる。
虚体・実体共に手足、特に足先が本人の自覚が無くても冷たく、
また本人が冷えを自覚している場合もあるが、逆気が元で起こる病気に罹りやすい。
≪腎膀胱全体の変動特徴:小腹痛み逆す。≫
腎一般:喀血(かっけ)・吐血・下血・生殖器病。
腎の虚:体重身冷・足腰寒く・小便赤黄色・消耗熱・物忘れ・精液不足・性欲減退・耳鳴り・眩暈・耳聾・
手足痺れ・食欲あって不食(食べられない)・下痢または便秘。
【 腎水経の変動 の参照リンクです。c208 】
〔心実の症状〕:喜び、良くない事も非常に喜び、笑う。
心経・注意欠陥他動性症候群・老人性の痴呆症・欝症状、
臓象論:心臓の変動反応:左に反応を触知。舌の諸症状。
舌が痺れる・舌の先が苦い・喋る時に舌の動きが悪い・舌が乾く・舌の口内炎。
身体が熱ぽく、不眠、苦しい。苦しみを伴う数脉・徐脉・不整脈。
瞬間的に意識を失う回数が多い。或いは患者の話す事と現実が時々一致しない。
〔心包、実すれば〕「心の臓」の邪実を表す、見逃さず、瀉法する。
胸内苦悶・心痛・呼吸促迫・特に不安感。
心包経の実について、普通には左の肝経の太衝穴を補えば、右の心包経の正実になる。
しかし、― 心包経に邪が客していると、流注上に湿疹や皮膚炎や異常物が現れる状態になり邪実を表す。
これは速やかに瀉すべき状態である。
≪心、小腸、心包、三焦の全体の変動特徴:身熱。≫
心の実:身熱・胃張る・四肢重し・大便不利・咽乾く。
心小腸の倶実:頭痛・身熱・大便難く・食胃より下らぬ・胸苦しく煩え臥すことが出来ぬ。
心包の実:心痛・面黄ばむ・目赤く・臂肘(ひじ)引きつる・腋下腫れ又痛胸脇張り重苦しい。
【 心火経の変動の参照リンクです。c205 】
症決定:心旺実証
比較脉状:腎虚・肝虚・心実・脾実・肺平
一番目の補法経:肝経の補法。
2014.6.14.
------------------
追伸
にほんブログ村
にほんブログ村
↑
鍼灸ブログ満載です。
ランキングにも参加しています。
クリックお願い致します。