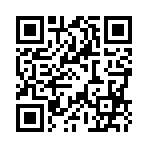五四難、病気が治る方向?
2013年12月17日
五四難、病気が治る方向?
ゆっくり堂の
『難経ポイント』 第五四難
※ 病気が治る方向に向かうか否かの参考図
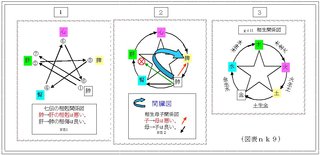
今回から山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 五四難のポイント其の一は、五四難の法則について。
五四難の法則:
臓病は治るのが難(むつか)しい。
腑病は治り易(やす)い。
※ 五四難のポイント其の二は、
病の証が相剋に伝わるものは治り難(がた)い。
※ 五四難のポイント其の三は、
病の証が相生に伝わるものは治り治り易(やす)い。
(難経原文)
五十四難曰.
藏病難治.府病易治.何謂也.
然.
藏病所以難治者.傳其所勝也.
府病易治者.傳其子也.
與七傳間藏同法也.
--------------------------
五四難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
五十四の難の解説をします。
臓病は治るのが難(むつか)しいが、腑病は治り易(やす)いとはどう言う意味かと。
お答えします。
臓病を治し難い理由は、病証の変化が相剋に伝わるからです。
腑病は治り易(やす)い理由は、病証の変化が相生に伝わるからです。
この五四難は前難(五三難)の七伝間藏の理論法則と同じである。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「五四難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.17.(今日は火曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
---------------------------
ゆっくり堂の
『難経ポイント』 第五四難
※ 病気が治る方向に向かうか否かの参考図
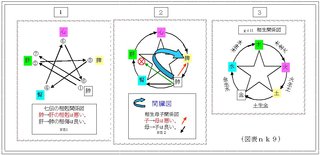
今回から山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 五四難のポイント其の一は、五四難の法則について。
五四難の法則:
臓病は治るのが難(むつか)しい。
腑病は治り易(やす)い。
※ 五四難のポイント其の二は、
病の証が相剋に伝わるものは治り難(がた)い。
※ 五四難のポイント其の三は、
病の証が相生に伝わるものは治り治り易(やす)い。
(難経原文)
五十四難曰.
藏病難治.府病易治.何謂也.
然.
藏病所以難治者.傳其所勝也.
府病易治者.傳其子也.
與七傳間藏同法也.
--------------------------
五四難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
五十四の難の解説をします。
臓病は治るのが難(むつか)しいが、腑病は治り易(やす)いとはどう言う意味かと。
お答えします。
臓病を治し難い理由は、病証の変化が相剋に伝わるからです。
腑病は治り易(やす)い理由は、病証の変化が相生に伝わるからです。
この五四難は前難(五三難)の七伝間藏の理論法則と同じである。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「五四難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.17.(今日は火曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
---------------------------
五二難、移動する病気?
2013年12月15日
五二難、移動する病気?
ゆっくり堂の『難経ポイント』 第五二難 ank052

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 五二難のポイント其の一は、
痛みが、一箇所に止まり慢性化しているのが臓病です。
痛みが、常に移動するのが腑病です。。
(難経原文)
五十二難曰.
府藏發病.根本等不.
然.
不等也.
其不等奈何.
然.
藏病者.止而不移.其病不離其處.
府病者.彷彿賁嚮.上下行流.居處無常.
故以此知藏府根本不同也.
--------------------------
五二難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
五十二難の解説をします。
臓病と腑病の発病の根本(状態)は同じものか、違うのかを問います。
お答えします。
同じではありません。
その状態はどの様に違うのか。
お答えします。
臓病は一ヶ所に止まって、他の部位には移動しません。
その病所もそこを離れません。
腑病は、あてもなく彼方此方にさまよい歩き、お湯が沸騰するように動く、
上や下に流れ行き、そして居る所なし。
(腑病は、病の根本があっても病所は一定の処に止まらず、あちこちと移行する。)
以上のように
臓病は病が動かず一ヶ所に止まっているのに対して、
腑病は常に移動する点で違いがあります。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「五二難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.15.(今年も後半月・・まだ半月・・今日は日曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
---------------------------
ゆっくり堂の『難経ポイント』 第五二難 ank052

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 五二難のポイント其の一は、
痛みが、一箇所に止まり慢性化しているのが臓病です。
痛みが、常に移動するのが腑病です。。
(難経原文)
五十二難曰.
府藏發病.根本等不.
然.
不等也.
其不等奈何.
然.
藏病者.止而不移.其病不離其處.
府病者.彷彿賁嚮.上下行流.居處無常.
故以此知藏府根本不同也.
--------------------------
五二難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
五十二難の解説をします。
臓病と腑病の発病の根本(状態)は同じものか、違うのかを問います。
お答えします。
同じではありません。
その状態はどの様に違うのか。
お答えします。
臓病は一ヶ所に止まって、他の部位には移動しません。
その病所もそこを離れません。
腑病は、あてもなく彼方此方にさまよい歩き、お湯が沸騰するように動く、
上や下に流れ行き、そして居る所なし。
(腑病は、病の根本があっても病所は一定の処に止まらず、あちこちと移行する。)
以上のように
臓病は病が動かず一ヶ所に止まっているのに対して、
腑病は常に移動する点で違いがあります。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「五二難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.15.(今年も後半月・・まだ半月・・今日は日曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
---------------------------
九難 臓病・腑病を判別
2013年12月13日
九難 臓病・腑病を判別する
ゆっくり堂の『難経ポイント』
第九難 ank09
今回も山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 九難のポイント其の一は、
脉診をして、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する法則を述べています。
※ 九難のポイント其の二は、
数脉(早い脈)は必ずしも身体に熱が出ると言う事ではない。
※ 九難のポイント其の三は、
「臓病」か「腑病」かを判別する問題は、五十二難と五十四難もあわせて学ぶべし。

(原文)
九難曰.
何以別知藏府之病耶.
然.
數者府也.
遲者藏也.
數則爲熱.
遲則爲寒.
諸陽爲熱.
諸陰爲寒.
故以別知藏府之病也.
--------------------------
九難の訳文
(井上恵理先生の訳文:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の訳文、福島弘道先生の訳文を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
九の難に曰く.
何を以ってか臓腑の病を別ち知るや。
然るなり。
遅は藏なり、遅は則(すなわ)ち寒となし、諸陰を寒となす。
数は府なり、数は則(すなわ)ち熱となし、諸陽を熱となす。
故に藏府の病を別ち知るなり。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
--------------------------
九難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
九の難の解説をします。
脉診上にて、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する根拠を説明しなさい。
お答えします。
臓病は、遅い脈を打ち、その理由は寒にあり、陰の性質を現わします。
腑病は、数脉(早い脈)を打ち、その理由は熱にあり陽の性質を現わします。
以上のように「臓病」か「腑病」かを判別して治療をしなさいと。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「九難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.3.(今日は13日の金曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
ゆっくり堂の『難経ポイント』
第九難 ank09
今回も山口一誠の考察文にて構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
※ 九難のポイント其の一は、
脉診をして、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する法則を述べています。
※ 九難のポイント其の二は、
数脉(早い脈)は必ずしも身体に熱が出ると言う事ではない。
※ 九難のポイント其の三は、
「臓病」か「腑病」かを判別する問題は、五十二難と五十四難もあわせて学ぶべし。

(原文)
九難曰.
何以別知藏府之病耶.
然.
數者府也.
遲者藏也.
數則爲熱.
遲則爲寒.
諸陽爲熱.
諸陰爲寒.
故以別知藏府之病也.
--------------------------
九難の訳文
(井上恵理先生の訳文:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の訳文、福島弘道先生の訳文を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
九の難に曰く.
何を以ってか臓腑の病を別ち知るや。
然るなり。
遅は藏なり、遅は則(すなわ)ち寒となし、諸陰を寒となす。
数は府なり、数は則(すなわ)ち熱となし、諸陽を熱となす。
故に藏府の病を別ち知るなり。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
--------------------------
九難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
九の難の解説をします。
脉診上にて、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する根拠を説明しなさい。
お答えします。
臓病は、遅い脈を打ち、その理由は寒にあり、陰の性質を現わします。
腑病は、数脉(早い脈)を打ち、その理由は熱にあり陽の性質を現わします。
以上のように「臓病」か「腑病」かを判別して治療をしなさいと。
--------------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「九難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.3.(今日は13日の金曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
八 難、生命の源
2013年12月11日
八 難、生命の源

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第八難 ank08
今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。
※ 八難のポイント其の一は、
人間の生命の源は「先天の気:腎間の動気」です。
※ 八難のポイント其の二は、
目が見えるのも、
耳が聞こえるのも、
感覚が敏感であるのも、
美味しい物を味わえるのも、
全て「先天の気:腎間の動気」が根本である。
人間を草木に例えれば、
根が腐れ無くなれば茎も、
葉も枯れ落ちて死んでしまうと。
(原文)八難曰.
寸口脉平而死者.何謂也.
然.
諸十二經脉者.皆係於生氣之原.
所謂生氣之原者.謂十二經之根本也.謂腎間動氣也.
此五藏六府之本.十二經脉之根.呼吸之門.三焦之原.
一名守邪之神.
故氣者人之根本也.根絶則莖葉枯矣.
寸口脉平而死者.生氣獨絶於内也.
--------------------------
八難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
八の難について。
「寸口の脉平にして」と言うのは、六部定位(ろくぶじょうい)で橈骨動脈を指腹に感じ診る時、
正常な脉(脈)なのに死ぬ人がある、これは如何なる理由なのか。
お答えいたします。
人間が健康体である為に十二経脉に気血が循り栄養しています。
それは「生気の原」と言う生命体としての根源的な力(命)が存在するからです。
生気の原とは、十二経の根本であると。原気の発生する所に生気の原があると。
それは腎間の動気を指していると。
「腎間の動気」これが五臓六腑の根本であり、十二経脉の根本であると。
そして呼吸の門(出入り口)でもあると。また三焦の原もここから発生していると。
前文を一つにまとめて言うと、
人間には自然治癒力がある。
これを「守邪の神」と命名する。
「先天の気」「腎間の動気」は人間が生きる根本である。
人間を草木に例えれば、根が腐れ無くなれば茎も、葉も枯れ落ちて死んでしまうと。
寸口の脉が平ら(正常)であっても死亡する人は、
生気・先天の気(腎間の動気)が独り内で絶えてしまうからである。
:::::::::
今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「八難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.11.(今日は水曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第八難 ank08
今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。
※ 八難のポイント其の一は、
人間の生命の源は「先天の気:腎間の動気」です。
※ 八難のポイント其の二は、
目が見えるのも、
耳が聞こえるのも、
感覚が敏感であるのも、
美味しい物を味わえるのも、
全て「先天の気:腎間の動気」が根本である。
人間を草木に例えれば、
根が腐れ無くなれば茎も、
葉も枯れ落ちて死んでしまうと。
(原文)八難曰.
寸口脉平而死者.何謂也.
然.
諸十二經脉者.皆係於生氣之原.
所謂生氣之原者.謂十二經之根本也.謂腎間動氣也.
此五藏六府之本.十二經脉之根.呼吸之門.三焦之原.
一名守邪之神.
故氣者人之根本也.根絶則莖葉枯矣.
寸口脉平而死者.生氣獨絶於内也.
--------------------------
八難の解釈
(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、
山口一誠の考察文にて構成しました。)
八の難について。
「寸口の脉平にして」と言うのは、六部定位(ろくぶじょうい)で橈骨動脈を指腹に感じ診る時、
正常な脉(脈)なのに死ぬ人がある、これは如何なる理由なのか。
お答えいたします。
人間が健康体である為に十二経脉に気血が循り栄養しています。
それは「生気の原」と言う生命体としての根源的な力(命)が存在するからです。
生気の原とは、十二経の根本であると。原気の発生する所に生気の原があると。
それは腎間の動気を指していると。
「腎間の動気」これが五臓六腑の根本であり、十二経脉の根本であると。
そして呼吸の門(出入り口)でもあると。また三焦の原もここから発生していると。
前文を一つにまとめて言うと、
人間には自然治癒力がある。
これを「守邪の神」と命名する。
「先天の気」「腎間の動気」は人間が生きる根本である。
人間を草木に例えれば、根が腐れ無くなれば茎も、葉も枯れ落ちて死んでしまうと。
寸口の脉が平ら(正常)であっても死亡する人は、
生気・先天の気(腎間の動気)が独り内で絶えてしまうからである。
:::::::::
今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。
参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「八難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.11.(今日は水曜日だ・・・)
---------------------------
---------------------------
七難、春夏秋冬の脉(脈)
2013年12月07日
七難、春夏秋冬の脉(脈)
ゆっくり堂の
『難経ポイント』 第七難 ank07
(図nk3)

※ 七難のポイント其の一は、
春夏秋冬の季節に応じて脉状は変化している。
※ 七難のポイント其の二は、
一年を六節に分けて、それぞれの脉状を述べてある。
(六節の区分は三陽三陰の少陽・陽明・太陽・太陰・少陰・厥陰です。)
※ 七難のポイント其の三は、
鍼灸師は四季に応じた脉状を認識して、季節に合った脉を作る事。
※ 七難のポイント其の四は、
現代社会(先進国)は夏には冷房、冬には暖房、放射能被爆、
大気汚染等と自然に身を任せた時代とは異質の状況にある。
よって、これも考慮して脉状を考察しなければならない。
(原文)七難曰.
經言.少陽之至.乍大乍小.乍短乍長.
陽明之至.浮大而短.
太陽之至.洪大而長.
太陰之至.緊大而長.
少陰之至.緊細而微.
厥陰之至.沈短而敦.
此六者.是平脉.將病脉耶.
然.皆王脉也.
其氣以何月各王幾日.
然.冬至之後.得甲子少陽王.
復得甲子陽明王.
復得甲子太陽王.
復得甲子太陰王.
復得甲子少陰王.
復得甲子厥陰王.
王各六十日.六六三百六十日.以成一歳.
此三陽三陰之王時日大要也.
--------------------------
解釈:
(本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の解釈より。山口一誠の考察文含む。)
七の難においては、黄帝内経・素問の平人気象論の三陽の部、より。
少陽の季節には、(ある時)大、小、短、長、と言う脉(脈)を打っている。
陽明の季節には、浮大にして短の脉を打っている
太陽の季節には、洪大にして長の脉を打っている。
太陰の季節には、緊大にして長の脉を打っている。
少陰の季節には、緊細にして微の脉を打っている。
厥陰の季節には、沈短にして敦(なん)の脉を打っている。
以上の六つの季節の脉は健康な人の正しい脉であるのか、あるいは病人の脉状であるのか。
お答えします。
これらは全て旺気の脉である。季節に相応する正しい脉状であると。
三陰三陽の気は自然界(天地)や人間の身体の内において旺気する月日はいつであるか、
又何日間であるのか。
お答えします。
少陽はその年の冬至の後の初めての「甲子(きのえ、ね)」から
次の甲子の前日「癸亥(みずのと、い)」の間である。
少陽の気が旺気するのは1回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二四年の冬至は12月21日です。
平成二四年の1回目の「甲子」12月29日から平成二五年の「癸亥」2月26日が少陽です。
陽明の気が旺気するのは2回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の2回目の「甲子」2月27日から平成二五年の「癸亥」4月27日が陽明です。
太陽の気が旺気するのは3回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の3回目の「甲子」4月28日から平成二五年の「癸亥」6月26日が太陽です。
太陰の気が旺気するのは4回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の4回目の「甲子」6月27日から平成二五年の「癸亥」8月25日が太陰です。
少陰の気が旺気するのは5回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の5回目の「甲子」8月26日から平成二五年の「癸亥」10月45日が少陰です。
厥陰の気が旺気するのは6回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の6回目の「甲子」10月25日から平成二五年の「癸亥」12月23日が厥陰です。
平成二五年の冬至は12月22日である。
平成二五年の冬至の後の初めての「甲子」は12月24日である。この日より少陽始まる。
旺気は60日間ずつあり、60日×6回で、360日すなわち1年となる。 閏調整ありです。
これが、三陽三陰に脉が旺気する月日の大要である。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
-------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「七難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.7.(今日は土曜日だ・・・)
---------------------------
ゆっくり堂の
『難経ポイント』 第七難 ank07
(図nk3)

※ 七難のポイント其の一は、
春夏秋冬の季節に応じて脉状は変化している。
※ 七難のポイント其の二は、
一年を六節に分けて、それぞれの脉状を述べてある。
(六節の区分は三陽三陰の少陽・陽明・太陽・太陰・少陰・厥陰です。)
※ 七難のポイント其の三は、
鍼灸師は四季に応じた脉状を認識して、季節に合った脉を作る事。
※ 七難のポイント其の四は、
現代社会(先進国)は夏には冷房、冬には暖房、放射能被爆、
大気汚染等と自然に身を任せた時代とは異質の状況にある。
よって、これも考慮して脉状を考察しなければならない。
(原文)七難曰.
經言.少陽之至.乍大乍小.乍短乍長.
陽明之至.浮大而短.
太陽之至.洪大而長.
太陰之至.緊大而長.
少陰之至.緊細而微.
厥陰之至.沈短而敦.
此六者.是平脉.將病脉耶.
然.皆王脉也.
其氣以何月各王幾日.
然.冬至之後.得甲子少陽王.
復得甲子陽明王.
復得甲子太陽王.
復得甲子太陰王.
復得甲子少陰王.
復得甲子厥陰王.
王各六十日.六六三百六十日.以成一歳.
此三陽三陰之王時日大要也.
--------------------------
解釈:
(本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の解釈より。山口一誠の考察文含む。)
七の難においては、黄帝内経・素問の平人気象論の三陽の部、より。
少陽の季節には、(ある時)大、小、短、長、と言う脉(脈)を打っている。
陽明の季節には、浮大にして短の脉を打っている
太陽の季節には、洪大にして長の脉を打っている。
太陰の季節には、緊大にして長の脉を打っている。
少陰の季節には、緊細にして微の脉を打っている。
厥陰の季節には、沈短にして敦(なん)の脉を打っている。
以上の六つの季節の脉は健康な人の正しい脉であるのか、あるいは病人の脉状であるのか。
お答えします。
これらは全て旺気の脉である。季節に相応する正しい脉状であると。
三陰三陽の気は自然界(天地)や人間の身体の内において旺気する月日はいつであるか、
又何日間であるのか。
お答えします。
少陽はその年の冬至の後の初めての「甲子(きのえ、ね)」から
次の甲子の前日「癸亥(みずのと、い)」の間である。
少陽の気が旺気するのは1回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二四年の冬至は12月21日です。
平成二四年の1回目の「甲子」12月29日から平成二五年の「癸亥」2月26日が少陽です。
陽明の気が旺気するのは2回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の2回目の「甲子」2月27日から平成二五年の「癸亥」4月27日が陽明です。
太陽の気が旺気するのは3回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の3回目の「甲子」4月28日から平成二五年の「癸亥」6月26日が太陽です。
太陰の気が旺気するのは4回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の4回目の「甲子」6月27日から平成二五年の「癸亥」8月25日が太陰です。
少陰の気が旺気するのは5回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の5回目の「甲子」8月26日から平成二五年の「癸亥」10月45日が少陰です。
厥陰の気が旺気するのは6回目の「甲子」の日より60日間である。
平成二五年の6回目の「甲子」10月25日から平成二五年の「癸亥」12月23日が厥陰です。
平成二五年の冬至は12月22日である。
平成二五年の冬至の後の初めての「甲子」は12月24日である。この日より少陽始まる。
旺気は60日間ずつあり、60日×6回で、360日すなわち1年となる。 閏調整ありです。
これが、三陽三陰に脉が旺気する月日の大要である。
詳しくは各先生の文献を参照されたし。
-------------------
今日もなんとか一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の「七難」をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.7.(今日は土曜日だ・・・)
---------------------------
六難「陰陽実虚」の診断は鍼灸の原則です
2013年12月05日
『難経ポイント』 第六難 ank06
※ 六難のポイント其の一、
「陰陽実虚」を脉診で診断する事は鍼灸術の原則である。

(原文)六難曰.
脉有陰盛陽虚.陽盛陰虚.何謂也.
然.浮之損小.沈之實大.故曰陰盛陽虚.
沈之損小.浮之實大.故曰陽盛陰虚.是陰陽虚實之意也.
--------------------------
訳文 (本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の訳文より。)
六の難に曰(いわ)く、
脉に陰盛陽虚、陽盛陰虚、有りとは何の謂ぞや。
然るなり、之を浮べて損小、之を沈めて実大、故に陰盛陽虚と曰う。
これ沈めて損小、これを浮して実大、故に陽盛陰虚と曰う。
是れ陰陽虚實の意なり。
--------------------------
少し更新が遅れました。
もなんとか今日も一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の六難をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.5.(今日は木曜日だ・・・)
---------------------------
※ 六難のポイント其の一、
「陰陽実虚」を脉診で診断する事は鍼灸術の原則である。

(原文)六難曰.
脉有陰盛陽虚.陽盛陰虚.何謂也.
然.浮之損小.沈之實大.故曰陰盛陽虚.
沈之損小.浮之實大.故曰陽盛陰虚.是陰陽虚實之意也.
--------------------------
訳文 (本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の訳文より。)
六の難に曰(いわ)く、
脉に陰盛陽虚、陽盛陰虚、有りとは何の謂ぞや。
然るなり、之を浮べて損小、之を沈めて実大、故に陰盛陽虚と曰う。
これ沈めて損小、これを浮して実大、故に陽盛陰虚と曰う。
是れ陰陽虚實の意なり。
--------------------------
少し更新が遅れました。
もなんとか今日も一難できたかな・・・?
詳しくは、こちらより入って下さい。。
そして、表の六難をクリックして本文をご覧下さい。
http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html
2013.12.5.(今日は木曜日だ・・・)
---------------------------