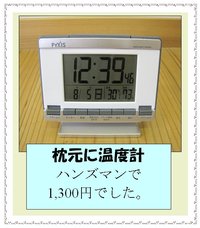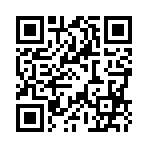「南北経驗醫方大成・病証論」の第二に寒論(かんろん)
2016年08月27日

夏でもストアーのお魚売り場の辺りは冷房が一段と強く、
身がブルッと震える事があります。
その症状が酷(ひど)くなるのを低体温症と言います。
そして低体温症による死を凍死と言います。
夏山の登山事故として2009年7月に北海道のトムラウシ山遭難がありました。
低体温症のことについて、
古(いにしえ)の「南北経驗醫方大成・病証論」の第二に寒論(かんろん)の話が論じられています。
・
※ 寒論を理解する為に井上恵理先生の講義解説のお話しを2本いたします。。
その後、私の寒論の現代風解説文を掲載いたします。
・
1:《身近に見られる寒の症状》井上恵理先生のお話し。
中寒を皆さんが一番身近に感じる事は、寒い時に凍える事が、まず中寒の一症です。
それから凍死がありますね。
あれは寒の邪が体の最も深い所にまで入ってしまったため死ぬんですね。
簡単に言うと、寒さにあって体が硬直して利かなくなるという事が、即ち寒邪に中てられたんだと考えて宣しいと思います。
・
2:《季節と身体》井上恵理先生のお話し。
この寒というのは、実は冬の気でありながら四時(四季)に渡って存在し、生体に影響を与える訳でして、春の寒、夏の寒、秋の寒、冬の寒と、それぞれの季節に寒が存在するんです。冬以外の季節の寒とはどういう事かと言いますと、
例えば夏、秋といった季節と我々の体は相順応すると東洋医学では考えられているのであります。
人体は小宇宙であるという考え方がありますが、我々の体は四時の気に応じて、その気に応じるような体に変化して行くんだという事です。で、
これは一番てっとり早く話をするのには温度の話をすれば良いのですが、例えば我々が冬に25度の部屋に居りますと、これは暑いという感じがあるはずです。
皆さんの治療室を25度に上げていてご覧なさい。これは暑いと患者さんも言うし、自分も暑いと感じるはずです。
ところが同じ25度でも、夏に25度の部屋にいたら今度は寒いと感じるはずです。
いわゆる科学的にいう所の25度という温度は何ら変わっていないのに、
我々の体に感ずる温度という物は夏も冬も同じ25度という具合には感じない訳です。
これは我々の体が四時の気に応じて変化している証拠だと言えます。
そういう意味で、冬ならば気温が零下前後の時に寒邪に中てられ易くなるが、夏は20度でも寒の邪に中てられる訳です。
ですから冬の登山には案外凍えて死ぬ人は少ないんです。
ところが逆に夏の登山で凍えて死ぬ人があるんです。
なぜかって言うと、夏我々が暑いと感じている時期に、先程言った様な20度くらいの温度に合うと、手がかじかんで来ます。
かじかむっていう事は、もう寒に中(あた)てられている状態で、もう感じなく成っているんです。
皆さんも経験あると思うんだが、かじかむつていうのは物をつかんだか何か動作をした時初めて、ああ俺の手はかじかんでるんだな、と気付きますね。
何もしない状態では寒邪に中てられている事を自分では分からないんです。
で、大成論の寒邪の始めに「寒は天地殺癘(さつれい)の気なり」と書いてある様に、中寒(ちゅうかん:寒邪が臓腑直接深く入り込む)の症状というのは、ふいに、急に、激しく来るんです。段々に来るんじやないんですね。
だから登山でよく死ぬ人があるというのは、疲れた上に寒邪に傷られているからなんです。
正常であれば傷られるはずないんです。
で、かじかんでいるという事は、手なんかは普通注意してれば分かりますが、足の指なんかは自覚的にはほとんど分か心ない。
分からない上に厚い靴をはいている物ですから、石なんかに乗っかる、足の指に力が無いから、カツとひつくり返って落っこちるという事ですね。
自分ではじっかり登ったつもりでも、足先の方が凍えているからそういう状態になって転落する事が多いんです。
・
南北経驗醫方大成、第二、寒論の解説文
・
※ 解説文は山口一誠のオリジナル文章です。
・
寒論(かんろん)
・
人体に害を与える外邪は6種類あります。
1風邪・2寒邪・3暑邪・4湿邪・5燥邪・6火邪です。
これを六淫(りくいん)の邪と言います。
そして、外邪の中で寒邪(かんじゃ)は最も威力の激しい邪気です。
寒邪は万物すべてを凍らせ死滅させる力を持った邪気です。
寒邪という物は四季を通じて存在します。
そして冬の季節を例に取れば、
草木は、冬になると寒気(寒邪)にさらされて葉を落とし枯木のようになり来春の若葉を育みます。
また、冬になると寒気(寒邪)から身を守るために鳥類や熊などは巣や穴の中にとじこもって冬眠します。
気力の虚弱な人、身体の虚弱な人、あるいは精神不安定で体調を崩しやすい人が仕事がら、あちこち行動している時に、
寒邪に身体を曝(さら)し犯されると、昏倒(こんとう)して人事不省(じんじ-ふせい)に成ります。
寒邪に身体を犯され時の症状を具体的に言いますと、
寒邪に中(あ)てられ凍(こご)えて口が利(き)けず話す事が出来なくなります。
また、手足が固く強張(こわば)ります。
それから筋緊張が強く出て疼(うず)く痛みを起こします。
あるいは、悪寒(おかん)が起きて、どんな事をしても震るえが止まらない状態に陥(おちい)ります。
また、とめどもなく、どんどん熱が高くなり顔が赤くなります。
また時として冷や汗が出ることも有ります。
寒邪に犯される人は五臓(肝心脾肺腎の臓)が虚弱な人達です。
そしてこれは冬だけに限らず、春にも夏にも秋にも季節を問わず寒邪の病気に陥る事があります。寒邪に犯された人の脉状は、遅(おそ)くって緊張(きんちょう)している脉状です。
寒邪に風邪が一緒になつて侵入した場合の脉状は、遅くって緊張し、かつ浮いていている脉状です。
そしてこの時の症状は、目まいを起こし、身体が麻痺して動かなくなります。
寒邪に湿邪が一緒になつて侵入した場合脉状は、遅くって緊張し、かつ「軟(やわ)らかい」脉状です。
そしてこの時の症状は、手足が腫れて痛みます。
寒邪に犯された人に対する治療方法の原則を述べます。
身体を温める補法の方法を取ります。
漢方薬では、補剤の生姜附子(ショウキョウブシ湯)を使用します。
鍼灸では、補法の手技を行います。
治療にあたっての注意点について述べます。
瀉法(しゃほう)を初めに行ってはいけません。
漢方薬では、吐法(吐かせる)とか下剤を用いることは厳禁です。
鍼灸では、瀉法の手技を最初に行なってはいけません。
寒邪に犯された人で治療の難(むつか)しい症状の鑑別(かんべつ)について述べます。
舌が喉の奥にひっかかってしまうとか、睾丸がグツと上に入ってしまう症状は難治性です。
・
以上、寒論の解説文を終わります。
・
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
・
———————————————-
病気が治らない理由。
仕事のやり過ぎ、遊び過ぎ、憂い思い過ぎ、房事過多の人、
養生しない人は病気は治らないと諦めた方が良いと思います。。
———————————————-
漢方家の方へ。
寒論を理解する為のお話し。井上恵理先生の講義解説より。
《寒と傷寒》p33-上段
ここで述べられている「寒(かん)」と、一般によく使われている「傷寒(しょうかん)」という考え方とは全く別の考え方であります。
[ 注・蛇足ながら説明すると、傷寒とは冬に寒邪を受けてその邪が経に入った場合、陽気が邪によつて閉じられ陽が鬱して熱となり、熱が経を伝わって行くもので、頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こす。
このような症状が冬に現れると正傷寒(即病傷寒)と呼び、春になって発病するのを温病(うんびよう)、夏になって発病するのを熱病(温病・熱病を合わせて不即病傷寒という)と呼ぶが、その原因はいずれも冬こ寒気に傷(やぶ)られた為であると考える。
即(すなわ)ち、 中寒(ちゅうかん)(冬期に限らず四季を通じて寒邪が臓腑に直接深く入り込んでしまった為に起こる症状)と傷寒とは異なった概念のものであることが理解される。]
ですから大成論で言うところの寒とは、中寒というものに相当するものだと思えば間違いありません。
・
・
ゆっくり堂鍼灸院HPには、
「第 論」の詳細解説 【井上恵理先生の講義解説】を掲載ています。
東洋医学の臨床に役立つお話が山盛です。
・
詳しくはHPをリンクしてご覧頂ければ幸いです。
http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/kr/
・
・
最後までお読み頂きありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。
ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。
そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。
よろしくお願いいたします。
にほんブログ村
鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking
ーーーーーーーーーーーーーー
2016.8.27. みゃちゃんブログ掲載
ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店
鍼灸師・薬種商:山口一誠
漢方相談員: 山口ひろこ
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
Posted by やまちゃん at 11:11 | Comments(0)
| 南北経驗醫方大成・病証論