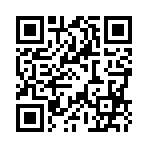12 五臓に風邪が中った時。
2012年04月02日
一、風論 :山口一誠の分類・考察。
南北経驗醫方大成・病証論の
五臓に風邪が中った時を、分類・考察します。

12. ○ 五臓と一腑に中った時の病状と脉証。
P23下段2行目~P28下段14行目より。
※ ここで述べられている脉証は、現在、東洋はり医学会が使用している、
比較脉診、別名を六部定位脉診と同じ場所です。
詳しくは、
次のHPの図gb31を参照ください。
http://you-sinkyu.ddo.jp/b207.html
※ ここのコーナーでは、井上恵理先生の講義から、
よみとれる事は、
「経絡治療の根本原則」として、
陰陽・虚実の調和、バランスを取る事が大切だと述べられ。
陰陽虚実の調整をするのが、
即ち経絡治療になると講義されています。。
井上恵理先生・講義録 本分より、
―〔大成論の文章を読み解く時に、経絡鍼灸家はつねに、〕
臨床的に考えないと意味が分かって来ない。・・・・とあります。
五臓すなわち、肝心脾肺腎と胃に風が中った時の症状と脉証が書いてあります。
「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 9行目辺りから。
若中於肝者、
人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
中於心者、
人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。
中於脾者、
人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。
中於肺者、
人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
中於腎者、
人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。
中於胃者、
両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。
ーーーーーーーーーーーー
井上恵理 先生の訳:
「大成論」:原文 9行目辺りから。。
若し肝に中る者は、
人迎と左の関上の脉、
浮にして弦、面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。
心に中る者は、
人迎と左寸口の脉、洪にして浮、
面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、
瘖(いん)していうこと能(あた)わず。
脾に中る者は、
人迎と右関上の脉、浮微にして遅、
四肢怠堕(ししたいだ)し、皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し身体通黄なり。
肺に中る者は、
人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、
面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。
腎に中る者は、
人迎と左尺中の脉、浮にして滑、
面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。
胃に中る者は、
両関の脉並びに浮にして大、
額上に汗多く、隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。
ーーーーーーーー
次に、肝心脾肺腎と胃に風が中った時のことを一つずつ述べます。
○ 肝の解説
〔原文〕
若中於肝者、人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
解説:まず、肝に中る物は、人迎と左関上(肝)の脉が共に浮にして弦。
― ここで述べられているのはどういう内容かというと、六部定位脉診〔比較脉診〕
によって、左関上(肝)の脉に病気があるという診断が立った上で、
しかも浮にして弦なる場合は・・・・という事なんです。
浮(脉)は風に中った時に現れる脉です。
弦(脉)は肝の脉です。
ですから浮弦という脉が摶っておれば、
どこに摶っていてもこれは「肝の証」だという事が脉状の上からも考えられるという事です。
ことに風というのは外邪ですから陽実を起す訳けです。
風に陰実なんて物はないんですから「肝の実」なんて事はありえない訳です。
そうすれば、肝が虚しているというのが当たり前なんです。
そうゆうふうに風は外邪なり、外邪は陽実なり、
という事を頭に入れて考えていかないと、
この文章は正しく理解が出来ないことになります。
〔原文〕
面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
解説:
面目多く青くというのは、
顔と目が青くなるという事で、
青は肝の色、目は肝の竅であるから、
これは肝の証である訳です。
〔原文〕悪風自汗、
解説:
悪風というのは悪寒とは違いますね。
悪寒とは、大きな熱が出る前にガタガタふるえてきて寒気がしてしょうがない状態で、いくら温かくしても、
寒さでガタガタふるのが悪寒です。
悪風とは、暖かい所に入ればふるえは止まる物で、
すきま風がスッーと入った時にガタガタくるのが悪風です。
悪風は風の邪に傷られた時に多く現れる。
自汗とは、じっとしていても汗がしとしと出てくる状態です。
自汗は、栄衛と関係していまして、
寒さに傷られると栄(血)が傷られ、
風に傷られると衛(気)が傷られる。
だから汗が出るとうい訳です。
〔原文〕左脇偏痛。とは、
ここでは、風が肝に入った時は片方だけ、左の脇腹が痛むという事です。
ーーーーーーーーーーーーーー
○ 心の解説
〔原文〕
中於心者、人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。
解説:
風邪が、心に中るものは、左手寸口(心)脉が、洪(脉)にして浮(脉)であるという事です。
そして、顔と舌が赤くなる。 舌は心の外候であり赤は心の色です。
翕翕(きゅうきゅう)というのは、とめどもなく、発熱する事です。、
瘖(いん)という字は「どもる」という意味で、
言葉を出す事が出来なくなるほど発熱する事です。
また、
ある古書には、この場合「うあ言」を言うという様にかいてあるようです。
-------------
○ 脾の解説
〔原文〕
中於脾者、人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。
解説:
脾に中るものは、人迎と右手関上〈脾)脉が、浮微(脉)にして遅脉。
そして、四肢怠堕とは、手足がだるくなるいう意味です。
皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)とは、皮と肉がぴくぴくと動く事です。
身體通黄とは、全身が黄色くなるそうゆう症状が起こるとうい訳です。
ーーーーーー
○ 肺の解説
〔原文〕
中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
解説:
肺に風邪が中るものは、人迎と右手の寸口(肺)脉が、浮濇脉にして短脉。
浮脉は風邪の脉で、濇脉は渋る脉のことで、濇(しょく)脉と短脉は「肺の脉」です。
面浮ばれというのは、顔が浮腫む、腫れぼったくなるという事です。
そして色が白くなってくる。
口燥とは、口の中がぱさぱさしてくる事をいいます。(別名は口渇です)
多喘とは、多くは喘す。 風が肺に中ると大抵は「ぜりつく」のです。
で、「嗽ス」と書いた本も多くあります。
咳嗽で、咳とは、声あって(咳きも出て)物(痰)もある症状で、
水気を含む事から腎にかかわるといわれています。。
「嗽ス」は、声あって物なしという症状で、痰が出てこない、
気だけ泄るので肺の物だと言われます。
「喘」という言葉は二通りに使われている。
1:咳嗽(がいそう)通じて「喘」と呼ぶ場合。
2:ただ単に「ぜりつく」つまり、喘息の発作時にみられる、
ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。
また、
「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、
これは陰陽共に虚という事を意味しています。(後で解説します)
ーーーーーーーーーー
○ 腎の解説
〔原文〕
中於腎者、人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。
解説:
腎に中るものは、人迎と左手の尺中(腎)脉が、浮にして滑脉。
面耳黒色とは、顔と耳が黒くなる。 腰脊痛み小腹にも来る。
隠曲とは、前陰道、即ち小便の出る穴です。
不利とは、小便がでなくなる。小便が少なくなるという事です。
-----------
○ 胃の解説
〔原文〕
中於胃者、両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。
解説:
胃が風に中った場合が書かれています。
胃が風に中ったものは、両方(脾と胃)の関の脉が並んで浮にして大の脉になる。
額上多汗とは、額(ひたい)にたくさん汗が出る事。
参考までに、隔噎(かくいつ)の病というものが、
この「大成論」にも「鍼灸重宝記」なんかにも出てきますが、
隔の病とは、食道の下の方の病、胃から見れば胃の上部、噴門部あたりの病です。
噎の病とは、食道の上の方の病で食道の侠窄部とか食道潰瘍とかの病を意味します。
隔塞不通とは、隔即ち食道の下の方が、塞がって通じない事です。
が、実際に塞がって通じない事ではなく、
自覚的に詰まったような感じがする事です。
食寒冷則泄とは、冷たいものを食べたり飲んだりすると下痢をするという事です。
ここまでが、風邪が五臓と一腑に中った時の病状と脉証であります。
:::::::::::
○ 肺の解説より関連講義-呼吸の陰陽・呼吸の虚実
呼吸の陰陽について。
〔原文〕
中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
「喘」という「ぜりつく」つまり、
喘息の発作時にみられる、ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。
また、「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、
これは陰陽共に虚という事を意味しています。
これに対して、咳というのは呼吸の呼気、吐く息のときだけの症状で、
吸う咳はありません。
このように、呼吸というものは、
陰気不足とか陽氣不足とかも表しています。
― 欠伸(あくび)は陰気不足による異常呼吸〔異常吸気〕です。
― クシャミや〔ため息〕・嗽は陽氣不足〔異常呼気、吐く息〕です。
※ 患者を診断している時、
脉を候ながら呼吸も候って、
その人の陰陽の状態を診るのです。
呼吸の虚実について。
呼吸に関してもう一つ大切な事は、
― 息を吸った時に身体は実してきます。―
― 息を吐くいた時に身体は虚してきます。―
だから、吐く息だけが多くなるという事は「虚」が成り立つ訳です。
経絡治療の根本原則。のまとめ、
【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療で根本原則。】
【 脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】
【 呼吸の陰陽・虚実の調和、
バランスを取る事が大切です。。
陰陽孤立せずという事です。
陰陽虚実の調整をするのが即ち経絡治療です。】
::::
経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の
ご意見・間違いの指摘・などを、
当院へお送りくだされば幸いです。
メール : yukkurido@ybb.ne.jp
まで。。。。。
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
ゆっくり堂 鍼灸院
山口一誠
住所 : 宮崎市天満2-4-26
http://you-sinkyu.ddo.jp/
メール : yukkurido@ybb.ne.jp
電話 : 0985-50-5174
礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・
のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
isseiちゃんヨリ・・・
2012.4.2- 月曜日・・
風論もあと少しです。
ふーとため息がこぼれる・・陽氣が。。。
南北経驗醫方大成・病証論の
五臓に風邪が中った時を、分類・考察します。

12. ○ 五臓と一腑に中った時の病状と脉証。
P23下段2行目~P28下段14行目より。
※ ここで述べられている脉証は、現在、東洋はり医学会が使用している、
比較脉診、別名を六部定位脉診と同じ場所です。
詳しくは、
次のHPの図gb31を参照ください。
http://you-sinkyu.ddo.jp/b207.html
※ ここのコーナーでは、井上恵理先生の講義から、
よみとれる事は、
「経絡治療の根本原則」として、
陰陽・虚実の調和、バランスを取る事が大切だと述べられ。
陰陽虚実の調整をするのが、
即ち経絡治療になると講義されています。。
井上恵理先生・講義録 本分より、
―〔大成論の文章を読み解く時に、経絡鍼灸家はつねに、〕
臨床的に考えないと意味が分かって来ない。・・・・とあります。
五臓すなわち、肝心脾肺腎と胃に風が中った時の症状と脉証が書いてあります。
「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 9行目辺りから。
若中於肝者、
人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
中於心者、
人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。
中於脾者、
人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。
中於肺者、
人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
中於腎者、
人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。
中於胃者、
両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。
ーーーーーーーーーーーー
井上恵理 先生の訳:
「大成論」:原文 9行目辺りから。。
若し肝に中る者は、
人迎と左の関上の脉、
浮にして弦、面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。
心に中る者は、
人迎と左寸口の脉、洪にして浮、
面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、
瘖(いん)していうこと能(あた)わず。
脾に中る者は、
人迎と右関上の脉、浮微にして遅、
四肢怠堕(ししたいだ)し、皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し身体通黄なり。
肺に中る者は、
人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、
面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。
腎に中る者は、
人迎と左尺中の脉、浮にして滑、
面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。
胃に中る者は、
両関の脉並びに浮にして大、
額上に汗多く、隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。
ーーーーーーーー
次に、肝心脾肺腎と胃に風が中った時のことを一つずつ述べます。
○ 肝の解説
〔原文〕
若中於肝者、人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
解説:まず、肝に中る物は、人迎と左関上(肝)の脉が共に浮にして弦。
― ここで述べられているのはどういう内容かというと、六部定位脉診〔比較脉診〕
によって、左関上(肝)の脉に病気があるという診断が立った上で、
しかも浮にして弦なる場合は・・・・という事なんです。
浮(脉)は風に中った時に現れる脉です。
弦(脉)は肝の脉です。
ですから浮弦という脉が摶っておれば、
どこに摶っていてもこれは「肝の証」だという事が脉状の上からも考えられるという事です。
ことに風というのは外邪ですから陽実を起す訳けです。
風に陰実なんて物はないんですから「肝の実」なんて事はありえない訳です。
そうすれば、肝が虚しているというのが当たり前なんです。
そうゆうふうに風は外邪なり、外邪は陽実なり、
という事を頭に入れて考えていかないと、
この文章は正しく理解が出来ないことになります。
〔原文〕
面目多青悪風自汗、左脇偏痛。
解説:
面目多く青くというのは、
顔と目が青くなるという事で、
青は肝の色、目は肝の竅であるから、
これは肝の証である訳です。
〔原文〕悪風自汗、
解説:
悪風というのは悪寒とは違いますね。
悪寒とは、大きな熱が出る前にガタガタふるえてきて寒気がしてしょうがない状態で、いくら温かくしても、
寒さでガタガタふるのが悪寒です。
悪風とは、暖かい所に入ればふるえは止まる物で、
すきま風がスッーと入った時にガタガタくるのが悪風です。
悪風は風の邪に傷られた時に多く現れる。
自汗とは、じっとしていても汗がしとしと出てくる状態です。
自汗は、栄衛と関係していまして、
寒さに傷られると栄(血)が傷られ、
風に傷られると衛(気)が傷られる。
だから汗が出るとうい訳です。
〔原文〕左脇偏痛。とは、
ここでは、風が肝に入った時は片方だけ、左の脇腹が痛むという事です。
ーーーーーーーーーーーーーー
○ 心の解説
〔原文〕
中於心者、人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。
解説:
風邪が、心に中るものは、左手寸口(心)脉が、洪(脉)にして浮(脉)であるという事です。
そして、顔と舌が赤くなる。 舌は心の外候であり赤は心の色です。
翕翕(きゅうきゅう)というのは、とめどもなく、発熱する事です。、
瘖(いん)という字は「どもる」という意味で、
言葉を出す事が出来なくなるほど発熱する事です。
また、
ある古書には、この場合「うあ言」を言うという様にかいてあるようです。
-------------
○ 脾の解説
〔原文〕
中於脾者、人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。
解説:
脾に中るものは、人迎と右手関上〈脾)脉が、浮微(脉)にして遅脉。
そして、四肢怠堕とは、手足がだるくなるいう意味です。
皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)とは、皮と肉がぴくぴくと動く事です。
身體通黄とは、全身が黄色くなるそうゆう症状が起こるとうい訳です。
ーーーーーー
○ 肺の解説
〔原文〕
中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
解説:
肺に風邪が中るものは、人迎と右手の寸口(肺)脉が、浮濇脉にして短脉。
浮脉は風邪の脉で、濇脉は渋る脉のことで、濇(しょく)脉と短脉は「肺の脉」です。
面浮ばれというのは、顔が浮腫む、腫れぼったくなるという事です。
そして色が白くなってくる。
口燥とは、口の中がぱさぱさしてくる事をいいます。(別名は口渇です)
多喘とは、多くは喘す。 風が肺に中ると大抵は「ぜりつく」のです。
で、「嗽ス」と書いた本も多くあります。
咳嗽で、咳とは、声あって(咳きも出て)物(痰)もある症状で、
水気を含む事から腎にかかわるといわれています。。
「嗽ス」は、声あって物なしという症状で、痰が出てこない、
気だけ泄るので肺の物だと言われます。
「喘」という言葉は二通りに使われている。
1:咳嗽(がいそう)通じて「喘」と呼ぶ場合。
2:ただ単に「ぜりつく」つまり、喘息の発作時にみられる、
ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。
また、
「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、
これは陰陽共に虚という事を意味しています。(後で解説します)
ーーーーーーーーーー
○ 腎の解説
〔原文〕
中於腎者、人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。
解説:
腎に中るものは、人迎と左手の尺中(腎)脉が、浮にして滑脉。
面耳黒色とは、顔と耳が黒くなる。 腰脊痛み小腹にも来る。
隠曲とは、前陰道、即ち小便の出る穴です。
不利とは、小便がでなくなる。小便が少なくなるという事です。
-----------
○ 胃の解説
〔原文〕
中於胃者、両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。
解説:
胃が風に中った場合が書かれています。
胃が風に中ったものは、両方(脾と胃)の関の脉が並んで浮にして大の脉になる。
額上多汗とは、額(ひたい)にたくさん汗が出る事。
参考までに、隔噎(かくいつ)の病というものが、
この「大成論」にも「鍼灸重宝記」なんかにも出てきますが、
隔の病とは、食道の下の方の病、胃から見れば胃の上部、噴門部あたりの病です。
噎の病とは、食道の上の方の病で食道の侠窄部とか食道潰瘍とかの病を意味します。
隔塞不通とは、隔即ち食道の下の方が、塞がって通じない事です。
が、実際に塞がって通じない事ではなく、
自覚的に詰まったような感じがする事です。
食寒冷則泄とは、冷たいものを食べたり飲んだりすると下痢をするという事です。
ここまでが、風邪が五臓と一腑に中った時の病状と脉証であります。
:::::::::::
○ 肺の解説より関連講義-呼吸の陰陽・呼吸の虚実
呼吸の陰陽について。
〔原文〕
中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。
「喘」という「ぜりつく」つまり、
喘息の発作時にみられる、ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。
また、「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、
これは陰陽共に虚という事を意味しています。
これに対して、咳というのは呼吸の呼気、吐く息のときだけの症状で、
吸う咳はありません。
このように、呼吸というものは、
陰気不足とか陽氣不足とかも表しています。
― 欠伸(あくび)は陰気不足による異常呼吸〔異常吸気〕です。
― クシャミや〔ため息〕・嗽は陽氣不足〔異常呼気、吐く息〕です。
※ 患者を診断している時、
脉を候ながら呼吸も候って、
その人の陰陽の状態を診るのです。
呼吸の虚実について。
呼吸に関してもう一つ大切な事は、
― 息を吸った時に身体は実してきます。―
― 息を吐くいた時に身体は虚してきます。―
だから、吐く息だけが多くなるという事は「虚」が成り立つ訳です。
経絡治療の根本原則。のまとめ、
【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療で根本原則。】
【 脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】
【 呼吸の陰陽・虚実の調和、
バランスを取る事が大切です。。
陰陽孤立せずという事です。
陰陽虚実の調整をするのが即ち経絡治療です。】
::::
経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の
ご意見・間違いの指摘・などを、
当院へお送りくだされば幸いです。
メール : yukkurido@ybb.ne.jp
まで。。。。。
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
ゆっくり堂 鍼灸院
山口一誠
住所 : 宮崎市天満2-4-26
http://you-sinkyu.ddo.jp/
メール : yukkurido@ybb.ne.jp
電話 : 0985-50-5174
礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・
のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
isseiちゃんヨリ・・・
2012.4.2- 月曜日・・
風論もあと少しです。
ふーとため息がこぼれる・・陽氣が。。。
Posted by やまちゃん at 16:24 | Comments(0)
| 南北経驗醫方大成・病証論