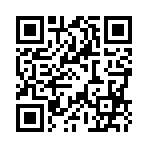東洋医学の原則理論に「内因なければ外邪入らず」と言う定義があります。五十一難更新しました。
2015年03月26日

ヒロコさんと小旅行の写真です。
東洋医学の原則理論に「内因なければ外邪入らず」と言う定義があります。
東洋医学の診断治療において、「内因なければ外邪入らず」の定義は常に当たり前なこととして貫かれています。
そして、今一度、この定義を井上恵理先生は難経第五十難を解説される中で述べられていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゆっくり堂の『難経ポイント』 第五十難
※ 五十難のポイント其の一は、
五臓に病が入った時の病症の名前として、虚邪、実邪、賊邪、微邪、正邪があります。
※ 五十難のポイント其の二は、相剋経の「賊邪」はこの中で一番悪い。非常に悪性です。
・
※ 難経四十八難臨床&エトセトラより。
「内因がなければ外邪は入らない。」
井上恵理先生の教え。
難経五十難の五邪の伝変から考察すると、風邪を引いた病症でも、補法と瀉法で治療する時がある。
ただ「邪が入ったから瀉せばいいんだ。」と考えるべきじゃない。―
病因と言うものは内因があって初めて外邪が入る様に出来ている。
何か内に不調和がない限り風邪は引くものじゃないですね。
素因あるいは内因が必ずあるはずです。
そこで私たち(経絡鍼灸家)は「内因がなければ外邪は入らない。」と言う定義(経絡鍼灸の法則)を立てた訳です。
だから現在の病状、熱がある・頭が痛いと言う時に治療をすると、
熱や頭痛は解消するが、なお身体にはまだ治療するべき根本的な内因が残らなくちゃならない。
だから内因の事を考えると完全治癒と言う事はない訳です。
そう言う風に考えて初めて広義な、広い意味での病気と言うものを観察しなくちゃいけないですね。
・
「内因なければ外邪入らず」の参考文。
「内因なければ外邪入らず」の経絡鍼灸の原則理論について。
「南北経驗醫方大成による病証論」井上恵理先生 講義録 より。
一、 風 論 11. ○ 病 因 P22上段1行目 ~ P23下段1行目より。
「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 4行目下部辺りから。
皆由氣體虚弱、榮衛失調、或喜怒憂思驚恐労役。
以眞氣耗散腠理不密。邪氣乗虚而入。
井上恵理先生の訓読
『 皆気体虚弱、栄衛調を失し、或は喜怒憂思驚恐労役に由(よっ)て、
以て真気を耗散し腠理密ならざるを致し、邪気虚に乗じて入る 』
井上恵理先生の解説:
これは〔1939年(昭和十四年)経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立された。〕
経絡鍼灸の治療の根本原則と相通じています。
どういう事かと言うと、病気になる原因として気体が虚弱である事、
つまり生まれながらのいわゆる素因という物、体質・個人差という物を第一に考え、
更に気血栄衛のアンバランスや七情の乱れとか労倦といった物を全部病因として扱っています。
真気というのは我々の身体を守っている所の全ての気の事で、
元来生気が足らないという素因の上に栄衛の失調とか内因あるいは労倦といった事によって真気を耗散すると条件が加わり、
その結果、腠理が緻密である事が出来なくなって風の邪が虚に乗じて入るんだと、こうゆう訳です。
だから、ここで経絡治療で根本原則と考える「内因なければ外邪入らず」と考え方があてはまる訳です。
風が有ってもですね、身体が正常で守りがしっかりしていれば邪に侵される事は無いのです。
古典に記載されている治療法、
つまり症状をあげてそれに対する治療をするという考え方、
例えば半身不随に対する治療法、あるいは人事不省に対する治療法もありますが、
その根本には気体虚弱という―「陰虚証」という考え方、
つまり陰の虚があるから邪が入るという考え方、これが最後に出てくる訳です。
ですから一つ一つの病症の治療法、
即ち標治法という物に加えて、本治法的な物の考え方をはっきり認識している事が必要だと思います。
またそれが我々のやっている治療の特徴でもある訳です。
経絡治療ではこうした体系があって、その中で色々な運用法をするという経絡治療で根本原則を立てる訳です。
・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゆっくり堂の『難経ポイント』第五十難のリンクはこちらをご覧ください。
http://yukkurido.jp/keiro/nankei/50nan/
・
最後までお読み頂きありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。
ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。
そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。
よろしくお願いいたします。
にほんブログ村
鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking
ーーーーーーーーーーーーーー
2015.3.26. みゃちゃんブログ掲載
ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店
鍼灸師・薬種商:山口一誠
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°
------------------------------
------------------------------
『難経ポイント』一難から八十一難までのHP掲載完成しました。
鍼術の要妙は、秋毫(しゅうもう)にあるものなり。
鍼術の極意は『虚実補瀉』である。難経七十二難。
どうして、鍼の刺入角度が45度で良いのか、その理由は?
当たり前すぎて語られない、鍼灸治療の神髄、難経六十九難。
女性には、腎経の陰谷穴を使えば良いですね。
鍼術の要妙は、秋毫(しゅうもう)にあるものなり。
鍼術の極意は『虚実補瀉』である。難経七十二難。
どうして、鍼の刺入角度が45度で良いのか、その理由は?
当たり前すぎて語られない、鍼灸治療の神髄、難経六十九難。
女性には、腎経の陰谷穴を使えば良いですね。
Posted by やまちゃん at 11:24 | Comments(0)
| 難経 ブログ勉強会