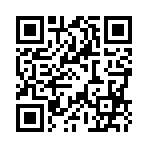昨日は鍼の研究会でした。新年会も。左肩こりの標治法。難経三十四難・三五難・三六難をアップしました。
2015年01月26日

昨日は鍼の研究会でした。
その後、恒例の新年会。
ヒラメの刺身と寄せ鍋、酔っ払たので放送禁止用語が炸裂していました。
鍼の研究会は、まじめにしていましたが、「気を漏らす」ゴチが出て、、
小里方式から、「左肩こり」標治法
使用した用鍼は、銀寸-1番鍼です。
左肩甲骨の際3か所に、
Nk先生の浅補深瀉の手法にて、硬結を直接、緩める手技を施す。
なお、所見の判別は、OY先生より、
表面が虚、深部に小豆2個分大のゴム粘土様所見を教えてもらい、
ここに手技を施しました。
手技の概要
捻鍼法の手技
1、押手を構え、鍼尖を痛みなくゆっくりと穴に接触。
2、刺手の手法は、示指を下にして母指を上に位置して、鍼柄を柔らかく挟み。
3、挟んだ鍼柄を示指と母指を鍼尖の方向にむけて、2ミリ幅ぐらいに鍼柄を撫でる。
(あるいは、示指は動かさず、母指のみを鍼尖の方向にむけて、鍼柄を撫でる手法。)
※ この「鍼柄を撫でる」手技は鍼尖の部位に催気を促す事になります。。
「鍼柄を撫でる」手技を3~5回やっていると、催気を感じます。
鍼柄を押すと鍼尖が刺入し進んで行きます。
4、「3」動作を優し繰り返すと、鍼尖が穴所に刺入してゆく。
5、浅補部にて、充分に補法を行い。さらに鍼尖が進むと目的の硬結部位に到達する。
6、硬結部位に到達したらこの硬結を緩める手技として、鍼の抜き差しを施す。
7、硬結部位の緩めが完了したら、
8、深瀉部はゆっくりと鍼を引き上げました。
険脉すると、本治法で整った脉が開いていました。
OY先生より、
「これは気を漏らした為に脉が開いた」との指摘を受けました。
反省、
硬結部位の緩めるまではよかったとおもいますが、
深瀉部より、浅補部もそのまま、鍼を引き上げましたので、
生気を漏らす事になったと考察されます。
ここでは、
深瀉部はゆっくりと鍼を引き上げ、
浅補部からは、押手の左右圧をスーッ加え、
すばやく抜鍼と同時に、鍼口を閉じる補法を行う。
手技をやるべきでした。
追記:患者役の先生の感想、
ものすごく肩は軽くなったとの事でしたが、・・
・
今年もこんな鍼研究会に月に2回参加します。
宮崎と東京で・・・・
・
難経三十四難・三五難・三六難をアップしました。
リンク先
http://yukkurido.jp/keiro/nankei/34nan/
http://yukkurido.jp/keiro/nankei/35nan/
http://yukkurido.jp/keiro/nankei/36nan/
・
・
最後までお読み頂きありがとうございます。
にほんブログ村
にほんブログ村
↑
鍼灸ブログ満載です。
お薦め!健康法
にほんブログ村
↑
健康ブログ満載です。
ランキングにも参加しています。
クリックお願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーー
2015.1.26. みゃちゃんブログ掲載
ゆっくり堂鍼灸院 山口一誠
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°